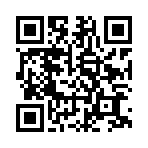2007年05月18日
清少納言を生んだ清原頼業公の舟遊び
紫式部と並んで、京都で有名なのが「清少納言」。彼女を生んだ清原家は、多くの歌人を生んだ事でも知られており、三十六歌仙にも名前が出てくる。
元々京の都を造るのに、遣唐使などに代々派遣された菅原家とともに、漢学者清原頼業公の存在は、実に大きく。ほとんど政治的実権を掌握できるほど信頼されていた。かの清原公が好んだのが舟遊び。和歌を楽しむのには、最高のシチュエーションだが、今日私たちは、「三船祭り」の関連行事として、毎年第三日曜日に、平安の宴を垣間見る事が出来る。
和歌からやがて物語へと展開していく日本の文学の原点が、町衆が受け継いだ祭りのなかで、拝見できる。
元々京の都を造るのに、遣唐使などに代々派遣された菅原家とともに、漢学者清原頼業公の存在は、実に大きく。ほとんど政治的実権を掌握できるほど信頼されていた。かの清原公が好んだのが舟遊び。和歌を楽しむのには、最高のシチュエーションだが、今日私たちは、「三船祭り」の関連行事として、毎年第三日曜日に、平安の宴を垣間見る事が出来る。
和歌からやがて物語へと展開していく日本の文学の原点が、町衆が受け継いだ祭りのなかで、拝見できる。
Posted by AKIYUKI KOYAMA at
00:43
│文学の都 安嘉の章 第6章
2007年05月15日
冷泉家
同志社の南西の一角に「冷泉家」が今に残る。
雅な年中行事が、今日も受け継がれている。
京都人なら誰もが知っているが、街の中には、「冷泉通り」の名を残す通りが数箇所ある。
日本人にとっての文学の原型の和歌。そして、言葉のリズム。
今日、京都には、城南宮をはじめ様々な和歌を楽しむ行事が受け継がれており、
様々な保存会が存在する。任天堂がバックアップした、『時雨殿』に代表されるように、
言葉を楽しむ伝統が、現在という時代になっても、子供たちの「かるた会」から
さらに「GS時雨殿」まで制作される背景に京都の脈々と受け継がれる文化が、
常にその時代を生きる人たちの熱き想いと時代のなかで楽しむ文化を受け継ぐ事によって
伝えられている。
そのシンボルの代表格の1つが、冷泉家の存在そのものである。
雅な年中行事が、今日も受け継がれている。
京都人なら誰もが知っているが、街の中には、「冷泉通り」の名を残す通りが数箇所ある。
日本人にとっての文学の原型の和歌。そして、言葉のリズム。
今日、京都には、城南宮をはじめ様々な和歌を楽しむ行事が受け継がれており、
様々な保存会が存在する。任天堂がバックアップした、『時雨殿』に代表されるように、
言葉を楽しむ伝統が、現在という時代になっても、子供たちの「かるた会」から
さらに「GS時雨殿」まで制作される背景に京都の脈々と受け継がれる文化が、
常にその時代を生きる人たちの熱き想いと時代のなかで楽しむ文化を受け継ぐ事によって
伝えられている。
そのシンボルの代表格の1つが、冷泉家の存在そのものである。
Posted by AKIYUKI KOYAMA at
01:08
│文学の都 安嘉の章 第6章
2007年05月11日
源氏物語と紫式部
世界で最も有名な日本文学は、やはり「源氏物語」であろう。
あまり文学に興味のない人でも、これが光源氏や桐壺・紫の上などの登場人物の事を、
少しは知っているだろう。この物語が書かれたのが、御所のすぐ東側の「魯山寺」そして、
紫の上との出会いの舞台も、式部ゆかりのお寺が舞台のモデルになったといわれている。
そのために京都では、様々な舞台が再現可能となり、ゆかりの土地を訪ね歩く事が
可能になってくる。
京都の魅力は、文学や歌舞伎他の様々な文芸のモデルが、身近に存在する事。
源氏物語から始まり、山村美佐サスペンスまで、文学が時に他の分野の再発見に結びつく。
撮影のメッカ、祇園新橋では、何人の殺人が行なわれ、何度舞妓さんが、辰巳神社にお参りに
いった事か?常に時代を超えた文学の舞台になっている。それが、文学に親近感と奥の深さを
与えるように思う。 続きを読む
あまり文学に興味のない人でも、これが光源氏や桐壺・紫の上などの登場人物の事を、
少しは知っているだろう。この物語が書かれたのが、御所のすぐ東側の「魯山寺」そして、
紫の上との出会いの舞台も、式部ゆかりのお寺が舞台のモデルになったといわれている。
そのために京都では、様々な舞台が再現可能となり、ゆかりの土地を訪ね歩く事が
可能になってくる。
京都の魅力は、文学や歌舞伎他の様々な文芸のモデルが、身近に存在する事。
源氏物語から始まり、山村美佐サスペンスまで、文学が時に他の分野の再発見に結びつく。
撮影のメッカ、祇園新橋では、何人の殺人が行なわれ、何度舞妓さんが、辰巳神社にお参りに
いった事か?常に時代を超えた文学の舞台になっている。それが、文学に親近感と奥の深さを
与えるように思う。 続きを読む
Posted by AKIYUKI KOYAMA at
01:07
│文学の都 安嘉の章 第6章
2007年05月06日
阿仏尼の命日
1222年に生まれ1283年5月6日に、
時代を開いた一人の女性がこの世を去った。
藤原為家の娘で、冷泉家に嫁いだ。
今日の和歌の源流が、この一人の女性によって始まる。
今日、娘と「下鴨神社」に行って祭りに参加したときふと思った。
このままふるさとに帰る・・・・・・といって
一人の女性が去っていった。
彼女の和歌における存在。
やがて、そこから世界的にも有名な文学が誕生した。
ちなみに我が娘は、「パープルチャン」
時代を開いた一人の女性がこの世を去った。
藤原為家の娘で、冷泉家に嫁いだ。
今日の和歌の源流が、この一人の女性によって始まる。
今日、娘と「下鴨神社」に行って祭りに参加したときふと思った。
このままふるさとに帰る・・・・・・といって
一人の女性が去っていった。
彼女の和歌における存在。
やがて、そこから世界的にも有名な文学が誕生した。
ちなみに我が娘は、「パープルチャン」
Posted by AKIYUKI KOYAMA at
00:04
│文学の都 安嘉の章 第6章